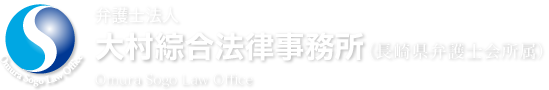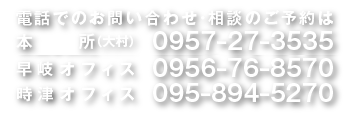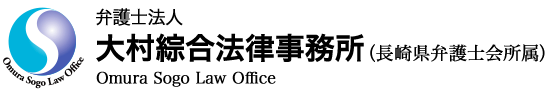相手方が示談に応じない場合は、どうしたらよいでしょうか。
相手方が交渉にも応じない場合には、訴訟や支払督促等の裁判手続きを行うことになります。
勝訴判決を得たり、裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方が支払いに応じない場合には、公正証書と同じように、強制執行することが可能になります。
また、状況に応じて、仮差押え等の保全手続きをとることもあります。
仮差押えとは、相手方から確実に回収するために、訴訟等が決着までの間、暫定的に、財産を差押える手続きのことです。
この手続きをとることにより、不動産であれば不動産登記簿に記載されますし、預貯金であればその払出しができず、相手方の金融機関からの信用が無くなりかねないことから、仮差押えをするだけで相手方が任意に支払いをしてくることもあり得ます。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
公正証書遺言とは、どのようなものですか。
公正証書遺言は、公証人が、証人2人の立ち会いのもとで、遺言者より聞き取った遺言の内容を筆記し、これに公証人、遺言者、証人2人が署名押印するものです。
公証人が遺言者の遺言であることを確認していますので、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、また、原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんされるといった心配もありません。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
検認とは、どのようなものですか。
遺言(公正証書による遺言を除く。)が残されていた場合、その保管者または発見した相続人は、家庭裁判所に遺言を提出しなければならず、この手続きを検認といいます。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと、開封しなければならないことになっています。
検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
債務名義とは、どのようなものですか。
債務名義は、請求権の存在,範囲等を表示した公の文書のことです。
強制執行を行うにはこの債務名義が必要であり、債務名義の代表的なものとしては、①確定判決、②仮執行宣言付判決、③仮執行宣言付支払督促、④公正証書(執行証書)、⑤和解調書や調停調書等があります。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
身内が逮捕された場合、どうしたらよいでしょうか。
刑事事件の被疑者は、弁護人に依頼する権利があります。
逮捕勾留中は、親族の面会が認められないことが少なくありませんが、弁護士の面会は認められます。
当番弁護士という制度があり、逮捕された方のほか、親族等も弁護士を呼ぶことができます。
また、弁護士費用を支払う余裕のない方でも、国(裁判所)が弁護人を選任する制度(国選弁護人といいます。)がありますし、逮捕された方本人や親族等が弁護人を選任することもできます(私選弁護人といいます。)。
刑事事件は時間的制約があり、一刻を争う場合も多いので、弁護人に依頼されることをお勧めします。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
寄与分とは、どのような制度ですか。
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした方がおられた場合に、遺産から寄与分を控除したうえで各相続人の相続分を定め、寄与のある相続人については、相続分に寄与に相当する額を加算するというもので、共同相続人の実質的な公平を図るための制度です。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
特別受益とは、どのような制度ですか。
相続人の中に、亡くなられた方(被相続人)から遺贈や生前贈与を受けている場合があり、この受けた利益のことを特別受益といいます。
被相続人から遺贈や生前贈与を受けている相続人は、相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割において、その特別受益分を遺産に持ち戻して(特別受益の持戻しといいます。)、相続分を算定する場合があります。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
相続調査はどのようにして行われますか。
遺産分割協議を行うには、まず、相続人の調査と相続財産(遺産)の調査をする必要があります。
相続人の一部を除外した遺産分割協議や相続人ではない方が加わった遺産分割協議は無効であり、除外された相続人は再分割を求めることができると解されていることから,相続人の調査は慎重に行わなければなりません。
弁護士は、職務上請求により、戸籍謄本や住民票の写し等の請求が認められていますので、この職務上請求により戸籍謄本等を取得し、相続人の調査をすることになります。
また、把握できていない相続財産があるような場合には、23条照会(弁護士会が、弁護士法23条の2に基づき、官公庁や企業、事業所等に問い合わせる制度です。)により調査することもあります。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
ブラックリストとは何ですか。
銀行や消費者金融等からお金を借りたり、信販会社の立替払いを利用して商品を購入したりした場合、指定信用情報機関に信用情報が登録されることになります。
信用情報には、信用取引に関する契約内容や返済状況・利用残高等の取引事実が載せられていますが、一般には、返済を一定期間遅滞した事実や債務整理をした事実が信用情報に登録されることをブラックリストといいます。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
ブラックリストへの登録の有無を確認する方法はありますか。
いわゆるブラックリストと言われているのは、日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター等の指定信用情報機関によって管理されている信用情報に、事故情報として掲載されることをいうものと思われますが、ご本人であれば、指定信用情報機関に照会することで開示を受けることができます。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑